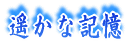
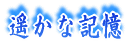
| ピンポーン、と軽い音を立てた呼び鈴に、パタパタと室内から音がする。 「はーい?」 その声と共に開かれたドアの向こう、声の主は綾人の顔を見て、驚いたように目を丸くした。けれどそれも瞬間の事で、すぐさま満面の笑みを浮かべ更に大きくドアが開かれる。 「あらまあ綾ちゃん、久しぶりねえ。お帰りなさい」 「うん、ただいま」 いつものようにそう返し、綾人は招かれるまま家の中へと入る。 「言ってくれてたら何か作っておけたのに、いつも綾ちゃんは突然ねえ」 「その方が伯母さん驚いてくれるから」 「別に驚かせてくれなくても結構よ。次からは前日には連絡頂戴ね」 「この前も同じ会話したよ」 「あら、だったら尚更次には連絡くれないと」 「うーん……難しいなー。ホラ、オレって思い立ったが吉日の人だから」 「知ってますよ。でも努力ぐらいはしてもらわないと」 「心がけます。………伯父さんは?」 「詳しくは聞いてないけど、講習会とか言ってたかしら」 「講習会ー?なに習いに行ってるの?」 「あら、逆よ逆。講師役ですって」 「あ?……何教えるの」 「ええーと……気軽に楽しむカクテル、だったかしら?」 「えーッいいなー。オレも教えて貰いたいなー」 「あら、綾ちゃん。バーテンダーになりたいの?」 「そうじゃないけど、最近伯父さんあんまり振ってないから、見たかっただけ」 言いながら綾人がシェイカーを振る真似をすると、彼女は可笑しそうに笑う。 「家で頼めば振ってくれるわよ」 「ダーメ。オレはまだ未成年だからって作ってくれないよ、絶対に」 「ああ、そうかもねえ。変な所で頑固だから」 クスクスと笑う彼女に続いて居間に入った綾人は、目に飛び込んできたそれに、目を丸くした。 「…………うわあ、何観てるの」 「え?ああ、アレ?懐かしいでしょう?」 「いや懐かしいっていうか…………」 「恥ずかしい?」 「……………………ちょっと」 問いかけに素直に頷くと、コロコロと彼女は笑い声を上げて、綾人の背を押し中に入るようにと促した。 「何だって、こんなの観てるの?」 「あら、こんなのって言い方はないでしょう?」 ソファへ座ったものの。目の前に繰り広げられる画像を見るのに酷く抵抗を覚えて仕方ない綾人の声に、彼女は心外だというように眉を寄せる。 「だーってさあ……。って言うか、こんなの撮ってたんだ」 「そりゃあもう、伯父さん大張り切りで毎回撮ってましたよ」 「そうですか………。で、何で今頃こんなの観てるの?」 「テープの整理も兼ねてDVDにダビングしてるのよー」 「え?」 「あら、何その驚き具合」 カチャカチャとお茶を入れる準備をしながら、彼女は更に心外だという風に顔を顰めて見せる。 「いや、だって………」 「伯母さん、機械苦手じゃないの?」 「……………そう」 問いかけを先に言われ、綾人は苦笑しながらも頷いた。 「私だって少しは世間の流れについて行こうと努力しているのよ、これでも」 そう答えながら、彼女は準備したお茶とお菓子を手に戻ってくると、綾人の前に腰掛けた。 「まあ、そうは言っても殆ど伯父さんが準備していってくれてますけどね。あと、解り易い手引書を作って貰ったし。それに書かれてあるままに作業してるだけだから、楽なものよ。あらまあ見て綾ちゃん、可愛いわねー」 その声に画面に目を戻すと、綾人はゲッと声を漏らす。 映っていたのは幼い頃の綾人自身。アンカーのたすきをかけ、必死の形相で走っている己の姿を可愛いなんぞ思える筈もない。 「………そうそう結局前を走ってる子を追い抜けなくって。それでこの後、悔しくて泣いちゃったのよねー」 「うそッ」 「ほーんと。見てて御覧なさい」 「って待って、それも撮ってるの?!」 「そうよー。それ見て撮ってる伯父さんまで涙ぐんじゃって、可笑しかったわねえアレは」 その時の事を思い起こしたのか、彼女はクスクスと笑いながらもティーカップに紅茶を注ぐ。はいどーそ、とか言いながらカップが差し出されたのだが、綾人はそれどころではない。 彼女の言葉どおり、画面一杯に自分の泣き顔が映し出されたからだ。 うああああ。 内心でそう声を上げ、恥ずかしさのあまり悶絶しそうな己を必死で押さえ、綾人は無理やり思考を目の前に置かれたティーカップに持っていく。 「ああ、そうだわ」 と、不意に彼女がそう声を上げるのに、思わず顔を上げる。と、再び視界に入るのはリレーから次の競技に切り替わってはいるが、同じように必死に走り回っている幼い頃の自分で、綾人は再びゲッとか何とか呻いてしまう。 「……………何?」 そんな綾人を綺麗に無視して、何やらゴソゴソと探し物をし始める彼女に、綾人はそう尋ねる。無論、TV画面から可能な限り視界を外しながら。 「…………………綾ちゃん、多分観た事無い筈だから、いい機会だわ、見せてあげる」 「何を?」 「良いモノ」 「え?」 この状況で『良いモノ』なんて表現をされて、素直に頷ける筈がない。ないのだが、だからといって嫌です、と返せる筈もない。 何だかんだ甘やかされている身ではあるが、同時にこの伯母には敵わないのも事実だし、同様に綾人も彼女には甘いのだ。 「何……?」 それでも不安な面持ちで尋ねる綾人に、ちょっと待って確かここら辺に……とか何とか言いながら、彼女はテープを探っている。 「ああ、あったわ。これこれ」 そう言って、彼女は編集中のテープを止める。 「って、ダビング中……」 「いいのよ、それはまた後できちんと編集し直してもらうから、伯父さんに」 「ああ、そう……」 「ええーと、こういう時は、どうするんだったかしらね」 等と呟く伯母に不安を覚え、結局は綾人が操作の続きを請け負った。 「頭からすぐに再生すればいい?」 「ええ」 「ん、分かった」 そう言って再生を始め、綾人はソファに座りなおす。正面に腰掛けていた筈の伯母も、気が付けば綾人の隣に座り、ティーカップを手にしていた。 「え………」 画面に映ったその映像に。綾人は小さくそう声を零す。 映し出されたのは、産まれて間もないだろう、赤ん坊。その子を腕に微笑むのは……。 「母さん………?」 呆然と、呟く。 幼い頃の記憶にあるその人よりも若いけれど。穏やかな微笑と、そして耳に馴染む優しい声。 そして。画像の後ろから応える、もう1つの声。若い張りのある男性の、それは。 「………父さん…?」 幼い記憶に、朧にしか残っていない、その人。アルバムの中に残るその姿も、数少ない………。 映し出されていくのは、産まれて間もない頃の自分と、それを取り囲む人たち。今も自分を見守り慈しんでくれている、伯父夫婦と、そして。……記憶の向こう、遥か遠くにしかなかった、両親。 ぎこちなく自分を腕に抱く、父の姿。泣きじゃくる自分をあやす、母の姿。それを見守る、今よりもずっと若い伯父と伯母の笑み。 季節は移ろい、少しずつ成長していく自分。 よちよちと伝い歩く自分を目尻を下げて見つめる、父の顔。その様を笑いながら揶揄する、楽しそうな母の声。無邪気に笑う、赤ん坊。 小さな手を、母の、そして父の大きな手に包み込まれ、桜の花の下を歩く自分。ひまわり畑の中、目を丸くして自分よりもずっと背の高いそれを見上げている自分と、そのまま後ろに倒れてしまわぬよう支える母。父の腕に抱かれ、その腕から落ちてしまいそうな程身を乗り出し、大きな水槽の壁に手をつける自分。 相好を崩す年若い夫婦。無邪気な笑い声。その傍らに常にある、穏やかな微笑み。 記憶にはない光景。けれども胸に染み入る、遠い記憶の向こうに確かに残る、感情。 「綾ちゃん……?」 穏やかな声に、ようやく綾人は我に返る。重ねられた手の温もりと、そして、頬を伝う何か。 自分が泣いているのだと気付くのに幾許かの時間がかかった。 悲しいわけでも、辛いわけでもないのに。 零れ落ちる涙は、止まらない。 「綾ちゃん?」 再びの呼び声に、綾人は涙を拭う。いつもならば決して自分に許せはしなかっただろう、伯母の前で泣いてしまった事を、けれど不思議と厭う気は起きなかった。 「……………本当は、貴方には見せないで置こうと思っていたのよ。伯父さんは、それは私達が決める事ではなくて、綾ちゃんが自分で決める事だって言ってたけど……。でも、どうしてかしらねえ。今日、貴方の顔を見たら、見せなくちゃって思ったのよ。貴方にちゃんと見せてあげなくちゃ、って。貴方のお父さんもお母さんが、どれだけ貴方の事を愛していたのかを、ちゃんと見せてあげなくちゃ、って」 「うん……」 「だから大丈夫よ」 「え?」 「たとえ綾ちゃんが何かに迷って躓いても、いつだって弘人さんと綾芽さんが見ていてくれてるわ。たとえ今、綾ちゃんの隣に居ないのだとしても、でも傍にいつだって二人はいてくれているわ。だから、迷わなくていいの。貴方の思う道を、信じて進んで良いのよ?」 「……………伯母さん……」 「勿論、私だって伯父さんだって、いつだって綾ちゃんの味方ですからね?」 「………うん」 いつから、彼女は気付いていたのだろう。 再び溢れた涙を隠そうと俯いた綾人の頭を、そっと抱き寄せてくれた伯母の温もりに、そう思う。 漠然とした、不安と焦燥。自分の進むべき道が分からなくて、ずっと、独り真っ暗な迷路の中を歩いている気がしていたのだ。もうずっと以前から。 別に両親が居ない事を恨んでいたわけではない。一人取り残されたのだと思っていたわけでもない。父親の記憶は確かに殆ど持ってはいなかったけれど、でも両親に愛されていたのだと信じる事は出来た。そして、伯父や伯母が、どれだけ心を砕いて自分を愛し、育て慈しんでくれたかも解っている。 だからこそ、このままでいいのかと。 我侭を言って、家を出た。一人で暮らす事で得る事も、解った事もある。けれど、本当にそれで良かったのか、と。必要以上の心配をかけてまで、彼らの元を離れる必要が本当にあったのか、と。 愛されているのだという、確かなその思い。過去も現在も、そして未来も。その思いがあるならば、進んで行ける。そう思う。 そして、今傍らにある温もりをも、もう一度自分の中に刻み付ければいい。 「伯母さん………」 「なあに?」 「………………今日、肉じゃが食べたい。伯母さん特製の」 ありがとう、とそう言いたかったのに。咄嗟について出たのはその言葉だった。 だって、何だか言い難かったのだ。抱き締められた状態で。 「あらまあ」 綾人の一言に、彼女はそう零し。それからクスクスと笑いながら綾人の頭をグリグリと撫で回す。 「ちょッ伯母さん?」 「あらまあ、肉じゃがなんかで良いのなら幾らでも作ってあげますよ。お持ち帰り出来る様にたくさん作りましょうねえ。他になにか食べたいのはないの?」 言いながら彼女は立ち上がり。 「綾ちゃんが食べるなら材料が足りないわね。伯父さんが帰ってくる前に買い物に行かなくちゃ。さ、手伝ってちょうだいね、綾ちゃん」 にこやかな笑顔と共の言葉に、クシャクシャにされた髪を苦笑いで整えながらも立ち上がり頷く。 大丈夫。 そう心の中で呟きながら。 |
| ■という事で。裏設定使用話、です。 『First〜』からのお話です。 ■この話を書いたきっかけは、前夜祭の字書き企画、でした。 実際の字書き企画の時には全く何も書けなかったのですが、 その後、不意に思いついたのがこのお話。 多少、お題の使い方に問題がないような気がしなくもありませんが。 お題が何だったかは………伏せておこうかと思われます。 使えてないジャンッ!ってお叱り受けそうなので……;; ■ええーとお話の設定時期としては、高校入って少ししたくらい、デス。 一人暮らしを始めて間もない頃、って言うか。 新しい環境にまだ馴染みきれてない頃、とも言えますかね。 ■なんだかいつも生意気にいきがってる感が作者にはあるキャラが綾人なんですが。 本当の部分では、こういう所もあるんだねーと。 自分でも書いててちょっと意外な発見をした気が致します(笑) |